- 遊び・生活の場としての機能、静養するための機能を備えた部屋またはスペースを指す。その他、支援の提供に必要な設備・備品等を備えなければいけない。
-
- 遊び … 室内である程度体を動かす
- 生活 … おやつを食べたり、本を読んだりしてくつろぐ
- 静養 … 子どもが体調の悪い時などに休息する

放課後児童クラブとは、一般的に「学童保育」と呼ばれている施設で、法律上の名称は「放課後児童健全育成事業」となっています。主に共働き家庭等の小学生に遊びや生活の場を提供して、健全な育成を図る施設です。
女性の社会進出、就労体系の多様化、核家族化、地域の繋がりの稀薄化等が進み、これからの時代では、放課後児童クラブのより良い「量的拡充・質的拡充」が求められるようになりました。今では国の政策課題にもなっており、2015年4月から本格に実施されている「子ども・子育て支援新制度」により、放課後児童クラブの制度も大きく変わりました。
「放課後児童健全育成事業」は、児童福祉法に基づいている事業のことで、主な対象・目的・役割が定められています。
放課後児童クラブの質を確保するために、施設の広さ、職員の資格および人数、子どもの数、開所日数や時間などを定めた「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が策定されました。
専用区画の面積は、児童1人につき1.65㎡以上と定められている。
ただし、既存の事業については施行から5年間で1.65㎡以上となるように努めなければいけない。

支援員は、支援の単位ごとに2人以上配置。
登録児童数が、40人を超える場合は、2つ目の単位を設ける。
ひとつの支援の単位を構成する児童の数(集団の規模)は、おおむね40人以下

職員は2名以上で、そのうち1名は
放課後児童支援員でなければならない(有資格者かつ研修修了した者)

1つの施設に、おおむね
40人以下の児童数が基本(超える場合は2つ目の施設が必要)
原則1年につき250日以上
土日・長期休業期間等 (小学校の授業の休業日) → 原則1日につき8時間以上
平日 (小学校授業の休業日以外の日) → 原則1日につき3時間以上
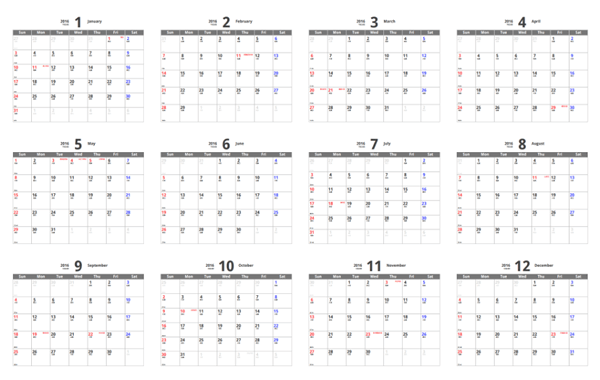
1年間で 250日以上
運営・稼働するのが基本
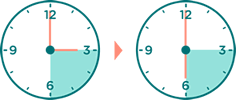
平日は3時間・土日祝は8時間が原則
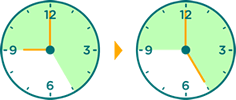
放課後や長期休みに子どもたちを預かる公的な施設を紹介します。

自治体が運営元となっている『公設公営』と自治体が設立して、運営は、NPO、民間企業や父母会などに委託している『公設民営』があります。場所は、小学校内の空き教室や児童館などを使用しています。

文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童クラブ」を一体的あるいは連携して実施しているものです。
| 放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ) |
放課後子ども教室推進事業 (放課後子ども教室) |
|
|---|---|---|
| 管轄省庁 | 厚生労働省 | 文部科学省 |
| 趣旨・対象 | 小学校に就学している子どもで、その保護者が労働・疾病・介護などにより昼間家庭にいない子どもを対象、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供 (児童福祉法第6条の3 第項に規定) |
全ての子どもを対象として、安全・安心な子どもの居場所を設け、地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動などの取り組みを推進 |
| 実施形態等 | 原則として年間250日以上開所 (夏休み等の長期休暇や、必要に応じて土曜日も開所) |
概ね年間を通じて断続的・単発的に実施 (平成20年は1箇所あたり平均126日) |
国として、共働き家庭等における「小1の壁」に対応するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、 多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備等を進めています。